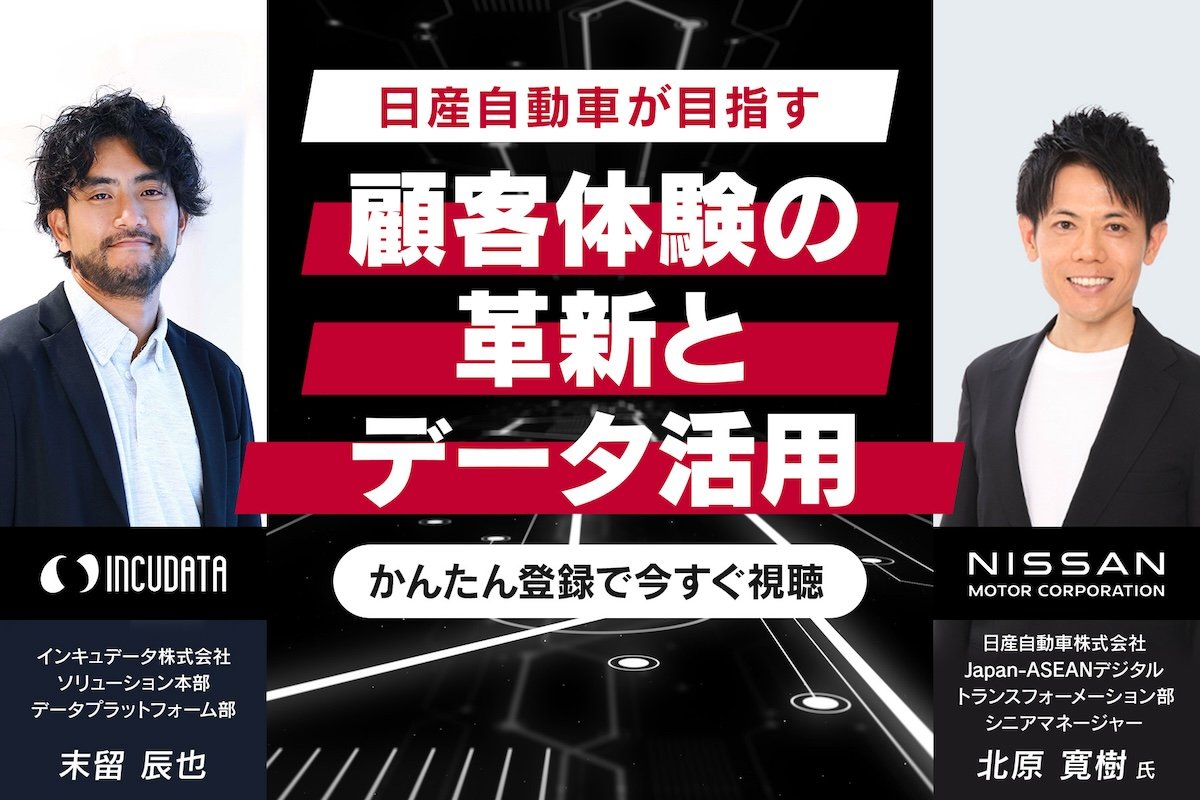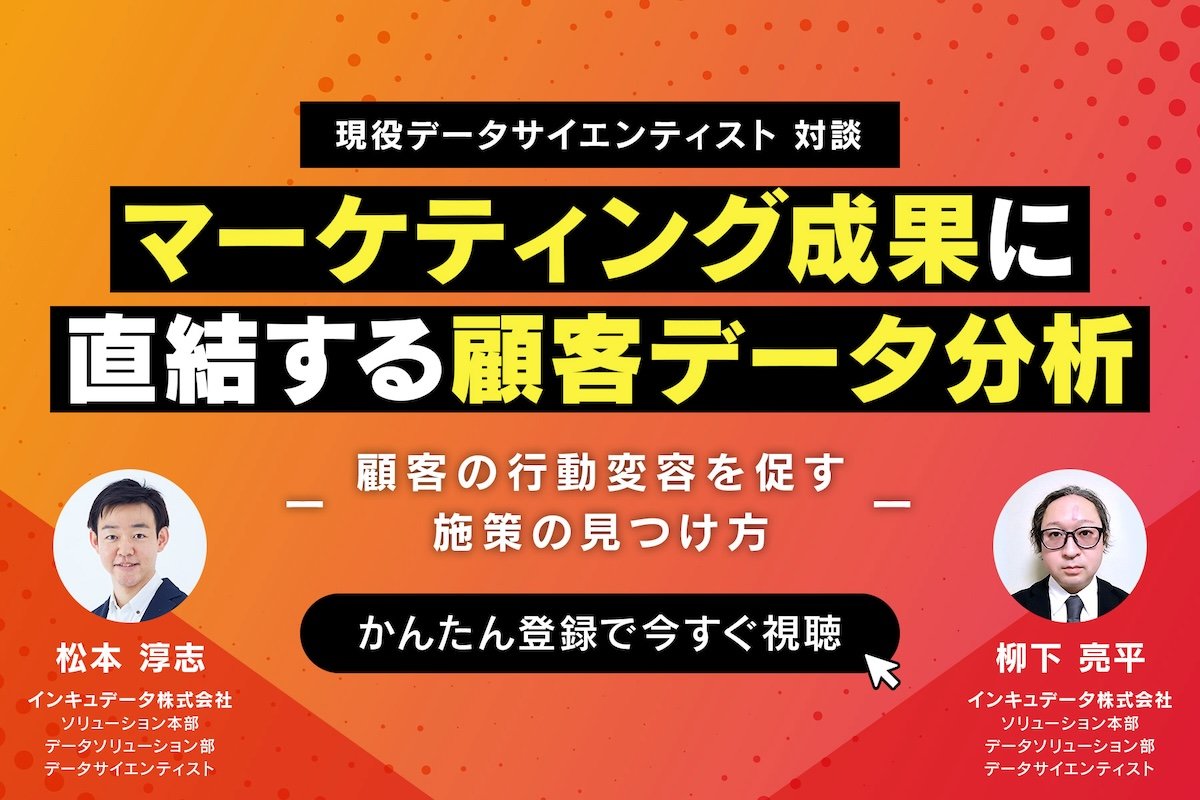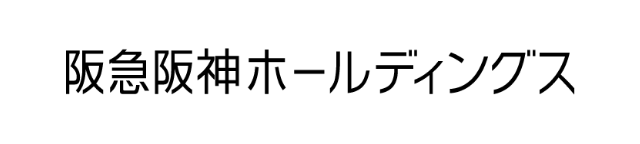Biz/Zine Day 2022 Summer イベントレポート - WHYからはじめるDXのビジネスデザイン - 自走のためのマインドやスキル、組織文化のデザインとは? -
2022年7月13日のBiz/Zine Dayは「デジタルで変える製造業の『組織』と『現場』」をテーマに開催され、各社が自社の取り組みやDX支援方法を紹介した。「データで、ビジネスはもっと面白くなる」を掲げてビジネス変革を支援するインキュデータ株式会社。同社でビジネスデザイン領域プリンシパルを務める河井健之助氏が、これまでの支援を通じて気づいた「多くの企業のDXでの悩みを解決する二種類のデザイン」について説明。その講演内容を紹介する。
河井 健之助 [講演者] / フェリックス清香 [著] / 黑田 菜月 [写] / 栗原 茂(Biz/Zine編集部) [編]
|
インキュデータ株式会社 ※講演当時 データアナリストとしてキャリアをスタートし、仏系広告代理店にて主に消費財・飲食・飲料・製薬・自動車業界の CRM戦略やマーケティング戦略、DX戦略やデータ統合など多岐に渡るプロジェクトをリード。その後米系クリエイティブファームにて新規プロダクト / サービス開発支援や体験設計、大手企業やスタートアップに対してクリエイティブ × データ思考やビジネスデザインの講師 / メンターとしてサポートするなど、企業と共創するパートナーとしてプロジェクトをリード。 |
6割の企業がDXに着手、一方で成果までは遠い道のり
河井健之助氏は講演冒頭、インキュデータで行った独自調査を紹介した。そこでは、およそ6割の企業がデータの利活用への取り組みや検討を始めているというものではあったが、デジタル化が目的となってしまうなどの理由から必ずしもDXの成功事例はまだまだ多くないようだ。河井氏のクライアントへの伴走の経験値からも、DXにおける“なぜそれを行うのか”という目的(WHY)、“どのように取り組むのか”という組織体制(How)に関して、悩みを抱えている企業が多いとした。
DX推進における「二つの課題」
河井氏自身は2021年4月にインキュデータに参画。そこから多くのクライアントと話す中で、DXプロジェクトの「目的」や「最終的なアウトカム(成果)」が社内で共有し切れていないと悩む企業が多いと実感している。また多くの企業がいずれはコンサルティングファームの支援から離れて、自走・内製化したいという意識を持っていると話す。しかし、そのやり方がわからないと悩む企業も多い。
つまり悩みは、「DXプロジェクトの目的、最終的なアウトカムなどを社内で合意形成できていない」「自走するために、人材や組織をどのように変えていくべきかわからない」の二つである。

DX推進における「二つのデザイン」
DXプロジェクトは、その目的、最終的なアウトカムに対する共通認識を、経営層だけでなく全社員で持っていないとならない。そうでなければ最終的にDXプロジェクトの成果を既存事業に取り込む際に、現場は負荷を感じるだけで意義が共有されずに止まってしまう。そこで、プロジェクトを進めるにあたっては、きちんと「なぜやるのか」から考え始めてビジネスをデザインすることが必要になってくる。つまりまず必要なのは「ビジネスデザイン」なのである。
またビジネスをデザインできても、実行する組織をコンサルティングファーム頼みではなく自走させていくには、挑戦を奨励するようなマインドセットや必要なスキルセット、企業文化が必要になる。つまり自社に合った「マインドセット・スキルセット・カルチャー」をデザインしなければならないのだ。

河井氏はこのDX推進に必要となる「二種類のデザイン」を考える上で参考になるとして、デザイン界の巨匠ジョン・ヘスケット氏のデザインの定義を引用する。
“Design is to design a design to produce a design.”
「デザインとはデザインを作る為のデザインをデザインすること」
「design」が一文の中で四つもあり、それぞれの意味は異なりそうだが、河井氏はビジネスデザインとは何かをこの一文に込めて解釈を加える。
「デザインという分野(A)は、成果の対象となるもの(D)を制作するために、そのコンセプトや企画(C)を構造化・翻訳する行為である(B)」

本質的な課題から価値を考える「パーパスドリブンなデザイン思考」

インキュデータ株式会社 ソリューション本部 ビジネスコンサルティング部 Principal Business Designer 河井健之助氏
さきほどの議論を踏まえると、ビジネスデザインを考える上で最も重要なのは「本質的な課題」なのではないか。この課題が捉えられていないと、きちんとしたビジネスデザインをすることはできない。「本質的な課題とは何か」に関して、河井氏はビジネスケースを例に挙げ説明した。

「子供がおもちゃを振り回しながら家の中を走り回っていた結果、子供部屋とリビングの壁に穴が開いてしまった。壁の修理を頼みたい」と希望する人がいたとする。その場合、壁の修理に着目して、「弊社の高機能壁材なら、もう二度と壊れませんよ」と返答するのがソリューションドリブンのベンダー思考の企業である。
また「本来、子供が子供部屋で遊んでいれば、おもちゃを振り回して家の中を走り回ることもないはず」だと考え、「子供部屋を明るい雰囲気で楽しい部屋にしましょう」とアイデアドリブン、代理店思考で提案することもできる。
この二つが間違っているわけではないが、もっとよく話を聞いてみると、相談者は「夫婦共に仕事が忙しいため、子供は寂しくて構ってほしいのではないか」と思っていることがわかることもある。そういったときに、本質的な課題は“子供の寂しさ”だと定義して、いっそ壁を壊して子供部屋をなくし、家全体がつながるような空間を作ることがソリューションだと提案することもできる。これがパーパスドリブンのデザイン思考での提案である。ビジネスデザインでは、このパーパスドリブンのデザイン思考で考えることが重要だ。
DX支援で起こりうる、ベンダー思考と代理店思考の弊害
たとえば、近年売上減少傾向にあり、トップダウンでDXを推進することが決まったとする。担当者は悩んだ末に、マーケティングデータを活用しよう、そのために事業部がサイロ化しているので、データを統合すれば何かしら結果が出るのではないかと考えてコンサルティング会社に連絡したとする。
すると、“ソリューションドリブンなベンダー思考”をするコンサルティング会社は、「データ統合であれば、このシステムを導入してデータ統合を進めていきましょう」と答えるだろう。一方、“アイデアドリブンな代理店思考”をするコンサルティング会社は、「マーケティングで今できていないこと、たとえば最適なコンテンツを配信してLTVを高めていきましょう」と答えるかもしれない。
しかし、実際には経営層も根本的な課題をよくわからないままDX本部を立ち上げている。担当者もマーケティングで解決できるのか、データ統合をしただけで課題が解決できるのかは、わからないまま依頼している。この場合、表面上の「何をどのようにするのか」ではなく、「なぜそれをやるのか」を起点にしないと、失敗することが多い。「DXとしてスーパーアプリを開発するためにSaaS基盤を導入したい」と希望する場合も同じだ。
なぜそのスーパーアプリを開発するのかと問われて、それにきちんと自分の言葉で発信できなければ、それは施策ドリブンのアプローチである可能性が大きく、結局は使われなかったり、浸透しなかったりする。
DXのビジネスデザインは「WHYからはじめよう」
インキュデータでは常に「なぜ、行うのか(WHY)」、それを「どうやって(HOW)、何(WHAT)を提供していくのか」という順序で、プロジェクトをクライアントと一緒に作り上げていく。「なぜ」の部分を自分の言葉で語れるようになるまで、支援は開始しないという。WHYを重視する姿勢は、社内のさまざまな部門を巻き込んでいくときにも重要だ。今後これをやる、そのためにはこういった基盤が必要だとWHATやHOWのみで話すだけでは社内はなかなか賛同してくれない。

「今、○○といった本質的な課題があるから□□をする必要がある」と、WHYを語ることが重要だ。これはプロジェクトレベルでも、企業全体のビジネス変革においても同様である。企業がなぜ、何のために存在するのかという企業のパーパスを考え、その上で組織が具体化したい「あるべき」状態をビジョンとして掲げていく。
ユーザの価値観が常に変化する時代でのビジョンの共創
ここで意識すべきことが一つある。コロナ禍で、働き方も買い物の仕方も大きく変わったように、ユーザの価値観は常に変化しているということだ。企業が一方的に「これは良いプロダクトである」と価値を提供しても、ユーザ体験は部分的に、一時的にしか向上しないことが多くなっている。

そこでユーザと共に目指すゴールやビジョンを定義し、それに向かって継続的に変化する必要がある。そしてユーザにどのような施策を打っていけばいいのか、皆が共通認識を持てる形で整理して、各プロジェクトに落とし込んでいくことが必要である。
ビジョンという明確な指針を持つことで、世界観は誰から見てもクリアなものになる。いったんゴールやビジョンを定義したら、それは常に意識すべきだ。その意識が足りないと、事業部Aと事業部Bがそれぞれ良い顧客体験を作ったとしても、企業の目指す方向と合わない可能性もあり、ユーザ同士も全く違うようなものになりかねない。
以降では、インキュデータが支援したケースから、いかにWHYからはじめるビジネスデザインを顧客と共創したのかを見ていこう。
WHYからはじめるビジネスデザイン「サービスビジョンの策定」
河井氏が紹介したのは、自然エネルギーによる発電事業を行う、大手エネルギー会社(A社)の事例である。停電を回避する必要があるため、A社では電力需供が逼迫しそうなときには、各小売電気事業者を通じて節電を呼びかけ、それに応じたユーザに金銭的なインセンティブを与えることで需給バランスを保つ、デマンドレスポンス(DR)事業を行っている。
しかし、今までのインセンティブは、エンドユーザに節電へのモチベーションを持ってもらいにくい状態だった。そこでA社では、金銭的なインセンティブをやめて店舗のクーポンなどに変え、外出を促すことで外出中の屋内の節電を測れないかというアイデアを持っていた。

小売電気事業者であるA社にとっては、自社顧客である店舗にクーポンの発行を依頼すれば、店舗へ付加価値を提供することになり、エンドユーザには外出による体験が提供できる。ただし、この取り組みにはさまざまなステークホルダが絡んでくることになり、巻き込み方が難しい。単純に店舗のメリット、ユーザのメリットを提示するのではなく、店舗やユーザと共創するサービスで目指す世界観を考え、どういうユーザ体験を提供すればそれが達成された世界になるのか、またA社としての企業ビジョン(ゴール)との一貫性がとれているかを、下図のように階層ごとに確認しながら進めていった。

検討の過程ではさまざまなアイデアが出てくるが、それを全て盛り込んでしまうとシャープなサービスではなくなってしまう。ユーザにとってはシンプルな体験の方が使いやすいことも多い。そこで、サービスビジョン・コンセプトの策定時にはサービスのコアバリューを必須項目、推奨項目、可能であれば入れたい項目、絶対に実行しないと誓う項目の四項目で整理し、キーワードとして言語化していった。
その結果、サービスビジョン・コンセプトにはプロジェクトに関わるパートナーが目指したい世界観や、ユーザが得られる体験など、サービスのコアバリューを表現したほか、視覚的にも伝わるようサービスロゴにもメッセージを込めている。

WHYからはじめるビジネスデザイン「KSFやPoCのデザイン」
インキュデータのビジネスデザイン支援は、サービスビジョン・コンセプトを策定するだけではなく、それが目指す世界観を実現するために、何がKey Success Factor(KSF)かを整理する。そして、それが本当に成功要因になるかを検証するためにProof of Concept(PoC)を二回行うことにした。PoCでの学びを今後に活かすために、理想的な顧客体験の整理と、PoCで検証すべき項目、目安になる数値、一回目と二回目で何を評価するのかもきちんと定義している。
さらに、PoC段階からサービスのローンチ以降も見据えて、事前に拡大戦略を策定。サービス拡大を実現する上で何が重要な論点になるかを整理した。
- サービス登録者数を獲得しているor獲得できる見込みが高いこと
- ユーザの行動誘発を促し、想定通り行動させることができていること
この二軸で何が必要になるのかを以下のように整理した。

たとえば、登録者数が多いのにユーザが行動していない場合には、提供体験が見直しになる。一方、登録者数が少ないもののユーザが行動する割合の高い場合は、認知や登録率の改善に対する打ち手が必要である。またもし登録者数も少なく、行動するユーザの割合も低い場合は原因を分解し、必要なピボットを考える必要がある。
策定したサービスビジョン・コンセプトは今年の夏と来年の冬、二回のPoCを経て実事業への転換をする目論見である。インキュデータはPoCにも参加することになっているという。
このようにインキュデータが支援するビジネスデザインは、WHYからビジョンを考えていく。DXによって達成する、クライアントとエンドユーザが共創する世界観のデザインから支援することで、全体の施策の一貫性と、企業のビジョンの一貫性を担保していく。WHYではなくWHATやHOWを起点にするとPoCを行って失敗してしまった場合はそこで終了になってしまうが、WHYからはじめれば、PoC後のピボットで新しい事業への展開も考えられる。PoCを無駄にせずに一貫性を持ったサービスが展開できるのである。

自走を可能にする、マインドセット・スキルセットやカルチャーのデザイン
「なぜやるか(WHY)」からビジネスをデザインできたあとは、自走するためのマインドセット・スキルセット・カルチャーフィットをデザインすることが必要だ。これはDXの中でも一番難しいものであり、それが達成できてこそDXの成功だといえると河井氏は強調する。インキュデータはこの点でも多数の企業を支援している。

大手証券会社でのデータマーケティングの課題
この企業では、それまでマーケティングといえばマスに対する画一的な宣伝のみ行っており、顧客の心を動かすコミュニケーションがなかった。それをDXによってデータを活用したone to oneマーケティングに変える取り組みを進めていたが、体制面での課題が多く、なかなか進まなかった。具体的には口座開設担当、国内株式担当、外国株式担当と部門が分かれていて、各部でKPIも異なる状態でデータが顧客一人ひとりに紐づいて取得できる状態にはなっていなかった。またデータ取得の効率が悪く、データの正確性にも疑いがある状態だ。そして部門を横断した顧客コミュニケーション戦略を把握する担当もいなかった。
口座開設後の取引開始率が800%アップ-その支援の中身
そこでインキュデータは全体のマーケティング戦略と、データ基盤を築くことを重視して支援を行った。その段階で、口座開設後取引開始率が800%アップになっている。加えて、インキュデータはマーケティング組織の育成を行った。具体的には、クライアントから未来の講師役としてオブザーバを選出してもらい、各部門から有望な若手マーケターを選出して、インキュデータのメンバーと共に「SWATチーム」を作り、マーケティング業務を遂行する。
最初は多くの部分をインキュデータのメンバーが行うが、次第にクライアント企業のメンバーが独り立ちできるように支援していき、彼らが業務をマスターすれば各事業部に戻って他のメンバーに伝授してもらう。
その際、それぞれの役割に応じて、スキルレベル、育成の目標レベルを明確に決め、全てのメンバーのレベルを自走化可能ラインから、エキスパートとして他メンバーを指導できるレベルに引き上げるためのマイルストーンやプロジェクトを定めることも含めて支援している。

部門横断のハブ機能として、自走できるまで伴走する
DX推進は全社横断的に進めることが必要である。支援を求める企業のリクエストに対応するだけでは進まない。インキュデータは本質的な課題が何かをクライアントと共に考え、ワンチームとして事業にコミットする支援方法をとっている。その際、最も重要なのがハブとしての役割である。経営層と現場では、想いやミッションが異なるため、使う言語が違うことも多い。全社横断の場合、横の組織との間では本音が言いづらいこともある。そういった場合にハブとしてインキュデータが入ることで円滑にコミュニケーションができることも多いという。
河井氏は以下のように言い添え、講演を締め括った。

「DXでは『なぜやるのか』を大事にしながらビジネスをデザインし、それを実装していくためのマインドセット・スキルセット・カルチャーも同時にデザインしていくことが必要です」